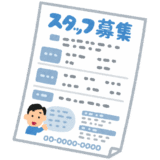滋賀県近江八幡市JR安土駅前で社会保険労務士をしている小辰です。
日本の労働環境を語るうえで欠かせない法律の一つに「労働基準法」があります。
労働基準法は、労働者が人間らしい生活を送りつつ安心して働けるよう、労働条件の最低基準を定めた法律です。
現在では当たり前となっている労働時間の上限や割増賃金、休日や休暇のルールなども、この法律によって整備されてきました。
しかし、この法律が最初から整っていたわけではなく、時代の変化とともに改正を重ねながら今日に至っています。
今回は少し毛色を変えて経営者、労働者共に身近な労働基準法の歴史について解説してみようと思います。
戦前の労働環境と制定への動き
戦前の日本においては、長時間労働や低賃金といった厳しい労働条件が一般的でした。特に工場労働に従事する人々は、過酷な環境で働くことを余儀なくされており、労働者の健康や生活は十分に守られていませんでした。
実は、日本でも労働者を守る法律を作ろうという動きは戦前から存在していました。1911年には「工場法」が制定され、労働時間や年少者の保護に関する規定が設けられました。
しかし、当時の工場法は対象が工場労働者に限られており、また規制も不十分で、実際の労働者の生活改善には大きな効果を上げることができませんでした。
このような背景の中で、より包括的な労働者保護の法律が求められるようになっていきます。
労働基準法の制定(1947年)
労働基準法が成立したのは1947年(昭和22年)のことです。戦後の日本は、連合国軍総司令部(GHQ)の指導のもと、民主的な社会制度の再構築が進められていました。その一環として、労働者の権利を保障するために誕生したのが労働基準法です。
労働基準法は、日本国憲法第27条「すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。」および第28条「勤労者の団結する権利」が背景にあり、労働者の基本的人権を尊重するための法律として位置づけられました。
制定当初の労働基準法では、1日8時間・週48時間労働の原則が定められ、時間外労働には割増賃金が必要とされました。また、年少者や女性労働者の保護、労働契約に関するルールなども整えられ、当時としては画期的な内容を持つ法律でした。
その後の改正と労働時間短縮の流れ
制定から70年以上の間に、労働基準法は時代の変化に応じて何度も改正されてきました。特に大きな焦点となったのは「労働時間の短縮」です。
制定当初は週48時間労働が原則でしたが、1987年の改正により「週40時間労働制」が段階的に導入されました。1997年には完全週40時間制が実現し、現在の労働時間の基本枠が整えられたのです。これにより、日本の労働者はよりゆとりのある生活を送ることが可能となりました。
また、1990年代以降は働き方の多様化に対応するため、裁量労働制や変形労働時間制といった柔軟な仕組みも取り入れられてきました。これにより、企業の実情や労働者の希望に応じた働き方ができるようになっています。
最近の大きな改正:働き方改革関連法
近年の労働基準法における大きな動きとしては、2019年4月に施行された「働き方改革関連法」が挙げられます。これは、長時間労働の是正や多様な働き方の実現を目指した一連の法改正であり、労働基準法も大きく見直されました。
具体的には、時間外労働の上限規制が法律で明確に定められました。原則として、時間外労働は月45時間・年360時間までとされ、臨時的な特別の事情があっても年720時間を超えてはならないなど、厳しい制限が設けられています。また、年5日の年次有給休暇の取得義務化も導入され、企業は労働者が休暇を確実に取れるように管理しなければならなくなりました。
さらに、高度プロフェッショナル制度の創設や同一労働同一賃金の導入などの仕組みも整備されています。
まとめ
労働基準法は、戦後間もない時期に誕生し、時代の要請に応じながら改正を重ね、労働者の権利を守り続けてきました。週48時間労働から40時間労働へ、そして長時間労働是正や有給休暇取得の義務化など、歴史の中でその役割は常に進化しています。
私たちが日常的に働く環境が守られているのは、労働基準法があるからこそです。
今後も社会や働き方の変化に応じて、この法律は新たな姿に進化していくでしょう。労働基準法の歴史を振り返ることは、これからの働き方を考えるうえでも大切なことだといえます。
最後までお読みいただきありがとうございました。